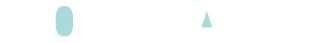コラム
【必読リスト】ホームページ制作でやってはいけないこと30選!(工程別)
近年は、知識がない人でも安価でホームページを作れたり、様々なサービスを提供する制作会社も増えてきました。けれども、専門知識を持たずにホームページを作ってしまうと、成果につながらないホームページに仕上がってしまうこともあります。
そういった失敗の原因は、ホームページを制作するにあたっての知識不足にあります。
そこで今回は、ホームページ制作や運用において、30のやってはいけないことをご紹介します。
CONTENTS
1.ホームページでやってはいけない設計

まずは設計の段階において、ホームページ制作においてやってはいけない3つの事柄をお伝えします。
目的を明確にしない
ホームページ制作における最大のタブーは、目的がはっきりしていないことです。
ホームページ制作の目的は、ページ数・ページの長さ・コンテンツ・デザイン・テキストなど全ての要素を決める時の軸になります。
「ホームページを作ること」自体を目的とするのではなく、「ホームページ経由の予約の数を増やしたい」「ホームページから資料請求に繋げたい」など具体的な目的・目標を定めましょう。
ターゲットを明確にしない
目的を決めたら、次にターゲットを定める必要があります。
同じ商品を売るにしても、10代の女子高生に売るのと、40代のサラリーマンに売るのとでは、効果的なアピール方法は当然異なります。
ターゲットがより魅力を感じるアピールポイントやデザインを考案するために、具体的なペルソナを定めましょう。このペルソナは、年齢・性別・職業・収入・興味関心など、細かく具体的に定めるほど方針が明確になります。
目標数値を明確にしない
最後に、目標数値を明確にすることも重要なポイントです。
目標数値がないと、具体的な施策に落とし込むことができません。
目標数値の具体例として、一般的に用いられるのは以下のような指標です。
- コンバージョン数:サイトの目的の達成数(問い合わせ数・資料請求数・予約数・購入数など)
- UU(ユニークユーザー)数:サイトを閲覧した人の数
- PV(ページビュー)数:閲覧されたページの数 など
しかし、例えば「売上◯%アップ」と目標を定めたとしても、ホームページ開設当初からすぐに目標達成ができるとは限りません。
まずはSEO対策でユーザー数を増やし、次にコンテンツの充実で滞在時間を伸ばすなど、段階的に目標を定めていく場合もあります。
2.ホームページでやってはいけない制作会社の選び方

次に、ホームページ制作を外注する場合に、制作会社選びでやってはいけないタブーについて解説します。
料金が適切だと分からないまま契約する
制作会社選びで、最も気になるポイントは料金でしょう。
ホームページ制作を初めて外注する場合には、複数の会社で見積もりを取り、その内訳までしっかり確認してください。他社より異様に高いのにその理由がはっきりしなかったり、内訳を詳しく説明してもらえない場合は、残念ながらあまり良い制作会社ではないかもしれません。
料金はホームページのクオリティにも関わるため、安いほど良いとは限りませんが、その料金が適切で無駄がないことが重要なのです。
リース契約などの長期契約で途中解約できない条件
ホームページは「作って終わり」ではなく、制作を依頼した会社に月額料金を払って運用管理を依頼する場合が多いです。
注意するべきなのは、この運用管理の契約内容。
契約によっては、運用管理の途中解約ができず、高額なコストを長期間払い続けなければいけないこともあります。途中解約できない契約の代表例が「リース契約」です。リース契約の提案をされた場合は注意し、内容をよく確認するようにしましょう。
制作スキルが高いかわからない
当然のことながら、制作スキルの高さは制作会社によって異なります。
望むような機能やクオリティのホームページが完成し、そして目標達成ができなければ、その制作会社に支払ったコストは結局無駄になってしまいます。
見積もりのほかに、実績や取引企業などをチェックし、確かな仕事が期待できる制作会社を選びましょう。
使いづらく利便性が低い独自のCMSを提供される
制作会社や開発者によっては、ホームページを制作する際にCMS(コンテンツマネジメントシステム)を採用する場合があります。
知識がない人でも更新や管理が容易になり、メリットは多いですが、中には使い勝手が悪いCMSも。
WordPressやMovable Typeなど一般的によく利用されているCMSなら問題ないことが多いですが、独自で開発しているCMSなどが提供される場合は利便性をチェックしましょう。
>>参考記事:【決定版】ホームページ制作会社の選び方!4つのコツと料金相場も紹介
3.ホームページでやってはいけない構築

ここからは、ホームページの制作において構築の段階でやってはいけないことを9つご紹介します。
モバイル(レスポンシブ)対応していない
モバイル対応(レスポンシブ対応)は、新たにホームページを制作するにあたって必須の要素です。
インターネットユーザーのほとんどが、スマホ、またはスマホとPCを兼用して閲覧を行っています。特にBtoCのサービス・商品を扱っている場合は、スマホの割合が高いでしょう。
モバイル対応していないと、多くのユーザーにとって使い勝手が悪く、様々な機会損失に繋がります。
>>参考記事:ホームページをスマホ対応させる方法!確認方法や外注する際の費用も解説
ページの表示速度が遅い
表示速度が遅いホームページは、閲覧するユーザーがストレスを感じやすく、そのページから離脱したいと思わせてしまいます。
一般的には、2~3秒以内にページが表示されるのが理想と言われています。
ページの表示速度が遅くなるのには、様々な要因がありますが、画像の大きさを調節することで改善する場合が多いです。
スピードチェックツールなどを利用して、ページ速度をチェックしておきましょう。
SSL化していない
SSLとは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みのことです。
第三者によるハッキングや改ざん、データの盗み見などを防ぐ役割があります。
SSLが導入されていないとセキュリティ上の問題があるほか、SEO的に不利になるという側面もあります。
全てのページをSSL化する「常時SSL」を制作会社に依頼するようにしましょう。
https://www.kbinfo.co.jp/web-service/
⇒「http」ではなく、「https」になっていればOK!
URLを正規化していない
「URLを正規化していない」とは、同じページを表示するためのURLが複数あるということ。
同じ内容のページが複数存在すると、検索エンジンの評価が分散されてしまい、SEO的に不利になります。
専門的なことがわからない人は、実際に依頼する制作会社や開発者に「URLは正規化されていますか?」と確認してみましょう。
構造化データのマークアップが正しくない
「構造化データのマークアップ」とは、コンピューター (検索エンジン)が効率的にWebサイトの情報を収集して解釈できるように、Webサイトのテキスト情報に意味を持たせて正しく認識させることです。
簡単に言うと、検索エンジンに効率的に見つけてもらいやすくするための対策です。
通常のマークアップのみだと、単なるテキストとして認識されてしまいますが、構造化マークアップをすることにより、そのテキストに意味を持たせられます。
これにより、さらにSEO対策を強化させることができるのです。
下記に具体的な構造化データのマークアップの例を記載します。
専門的な内容で難易度が高いため、制作業者に依頼するのがおすすめです。
(例)
●通常のマークアップの場合
<div>株式会社◯◯</div> ←単なるテキストだと認識される
●構造化マークアップの場合
<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Corporation”>
<span itemprop=”name”>株式会社◯◯</span> ←「株式会社◯◯」という“名前”だと認識される
</div>
パンくずリストがない

パンくずリストとは、今ユーザーが閲覧しているページが、ホームページのどの位置にあるのかを示してくれる地図のようなもの。
一般的にはホームページ上部などに、「ホーム>メニュー>カテゴリ名>記事名」などと記載されているものです。
見落としがちな要素ですが、ユーザビリティの面でもSEOの面でもパンくずリストは重要になります。
制作会社なら基本的につけてくれるものなので、ホームページ制作に直接携わらない人も知識として知っておきましょう。
内容が重複しているページがある
サイト内外を問わず、内容がコピーしたように重複しているページがあると、SEO的に弱くなります。
Googleのアルゴリズムによって、重複した内容のページがある場合は、後から掲載されたコンテンツの方が検索順位が下がるようになっているためです。
重複したコンテンツがあまりに多いと、サイト全体の評価が下がったりペナルティを受けることもあるため注意しましょう。
ページ遷移が多い
情報が分散していて、複数のページを移動しないと欲しい情報が手に入らないような構造だと、ユーザーはストレスを感じます。重要な情報をなるべくコンパクトにまとめ、ページ遷移を少なくすると、シンプルで見やすいホームページになります。
「トップを見るだけで主旨がわかる→詳細を知りたい事項は個別ページに移動する」という構造が、わかりやすくておすすめです。
>>参考記事:効果的なホームページ構成の考え方は?テンプレートもご紹介
無料のレンタルサーバーを使う
サーバーには無料のものと有料のものがありますが、事業用のホームページを制作するなら無料のレンタルサーバーはおすすめできません。
コストは抑えられますが、「容量が著しく小さい」「WordPressなど一部のCMSが利用できない」「利用できるドメイン数に制限がある」「サポートがない」などのデメリットがあるためです。
そもそも、しっかりした制作会社が無料のレンタルサーバーを勧めることは少ないので、そのような提案を受けたら注意するようにしましょう。
4.ホームページでやってはいけないデザイン
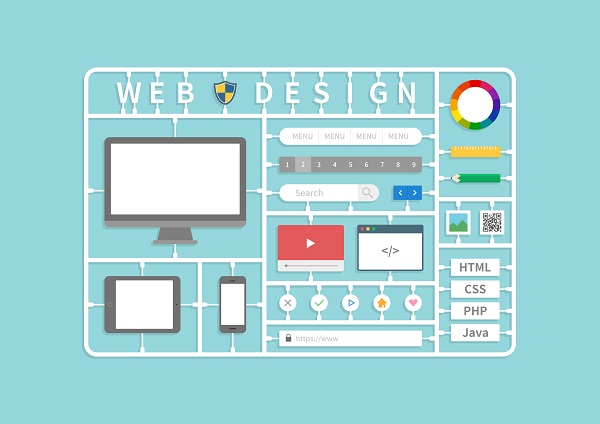
次にご紹介するのは、デザイン面でやってはいけない事柄5つです。
コンセプトや訴求したいことが伝わりにくい
デザインは、ただ見た目を格好よくするためだけではなく、伝えたいことを伝えるためにあります。
コンセプトや訴求内容にあっていないデザインは、どれだけ見た目が良くても意味がないのです。
ホームページのデザインは、何より「伝わりやすさ」が重要になります。
ターゲットとデザインが合っていない
訴求したいターゲットによって、当然ながら効果的なデザインは異なります。
中高生に安価なアクセサリーを売りたい場合と、中高年層に高級なジュエリーを売りたい場合では、お店のデザインや雰囲気を変えるのと同じです。
ただし「女性がターゲットだからテーマカラーはピンク」など、思い込みがベースになったデザインは逆に敬遠されることも。
ターゲット層に実際に人気のファッション、ブランド、アプリ、トレンドなどの要素を分析し、より興味を引くデザインを考案しましょう。
デザインやメッセージに統一感がない
ホームページ内のデザインやメッセージに統一感を持たせることを「トンマナを揃える」といいます。
トンマナとは「トーン&マナー」の略で、色のトーン、文字・画像の大きさ、フォント、レイアウトなどをサイト全体で揃えることをいいます。
要素ごとのデザインは魅力的でも、全体で統一感がないとちぐはぐな印象になり、見づらいホームページになってしまうため注意が必要です。
視認性が低い
文字や写真を小さめに表示して余白を大きく取るデザインは、すっきりとおしゃれな印象になるため近年流行しています。
しかし、あまりに文字が小さすぎると視認性が低くなり、テキストが読みにくくてユーザーのストレスになります。
文字の大きさは最低でも12ピクセル以上にして、視認性を保つのがおすすめです。
また、レスポンシブルデザインの場合はPC・スマホ・タブレットなど、どのデバイスでも見やすいページになっているかどうか確認しましょう。
>>参考記事:【保存版】WEBデザインの参考にしたいギャラリー・サイト集13選
5.ホームページでやってはいけないSEO対策

ここでは、ホームページのSEO対策について、やってはいけないポイント4つを押さえておきましょう。
文章にキーワードを詰め込む
SEO対策において、キーワード数が多ければ多いほど有利になると思っている人も多いです。
しかし、キーワードを詰め込みすぎた不自然な文章は、逆にSEO的に不利になってしまいます。
不正なSEO対策はブラックハットSEOと呼ばれ、ペナルティの対象にもなり得ます。
SEO対策を意識するとしても、キーワードは自然に見える範囲で入れ込むようにしましょう。
meta keywordsにキーワードを詰め込む
Googleなどの検索エンジンの技術が未発達だった時代は、「meta keywords」がコンテンツの内容を理解する手助けとして利用されていました。
しかし現在では、meta keywordsはGoogleにサポートされているメタタグに含まれていません。
そのため、meta keywordsに何を記入しても、SEO対策的には意味がないと言えます。
不用意にキーワードを入れてしまうと、競合にどのキーワードで対策しているかが知られてしまうので、meta keywordsにはキーワードを詰め込まないようにしましょう。
外部リンクを購入する
外部サイトからの「被リンク」はSEO対策の要素の1つです。
しかし、どんな被リンクでもいいというわけではありません。過去には「数」が重視されている時代もありましたが、現在は「有料リンクの購入」「関連性の低いサイトからの被リンク」「リンク集サイトからの被リンク」は意味がなくなっています。
特に有料リンクの購入は「品質に関するガイドライン」に対する違反と見なされ、ペナルティの対象になることもあるため要注意です。
画像の容量が大きすぎる
サイズが大きすぎたり、画質が良すぎる画像を使用すると、ページの表示に時間がかかります。
そうなると、ユーザーがストレスを感じて滞在時間が短くなるほか、表示速度が遅いことは検索順位にも影響します。
ホームページに画像は不可欠ですが、1枚100KB程度を目安として容量の小さい画像を使用するようにしましょう。
>>参考記事:ホームページのSEO対策をしたい人必見!SEO対策の必要性や費用を解説
6.ホームページでやってはいけないコンテンツ制作

コンテンツ制作において、やってはいけないポイントは以下の3つがあります。
著作権や個人の権利の侵害
フリー素材ではない画像やイラストなどを勝手に利用するのは、元コンテンツを作成した会社や個人の著作権の侵害になります。
人が写っている写真の場合、肖像権やパブリシティ権、プライバシー権などの侵害になることも。
訴訟や炎上のリスクがあるため、画像や文章の無断利用は避け、有料コンテンツは規約を守り、ライセンス料を支払って適切に使用しましょう。
薬機法などその他法律に反する記述
健康、医療、美容などに関わるホームページの場合、薬機法に注意が必要です。
医薬品、医薬部外品、化粧品などには広告規制があり、不正確な情報を掲載すると薬機法違反になる可能性があります。
薬機法以外でも、コンテンツに関連する法律や法規制には気をつけてホームページを制作しましょう。
掲載内容のファクトチェックをしっかりと行い、外部の情報を引用する場合は信頼できる機関の情報のみに絞るのが大切です。
他サイトの文章のコピーや画像の無断引用
他サイトの文章や画像を無断でコピーして掲載することは、先にお伝えしたように著作権法違反になります。
ただし「引用」については、ルールを守って行えば違法にはなりません。
違法にならないポイントは、「オリジナルの文章を補強・補完する意味合いで使用する」「引用元を明示する」の2つ。
無断でのコピペは避け、引用を行う場合はルールを守って行いましょう。
7.ホームページでやってはいけない運営

最後に、ホームページの運営について、やってはいけないポイント2つをお伝えします。
更新を怠る
せっかく制作したホームページも、作りっぱなしで更新を怠っては意味がありません。
例えばコーポレートサイトの場合、更新が長期間止まっていると事業が停止しているのでないかと誤解を生んだり、問い合わせが減る可能性があります。
また、長期間更新がないサイトは検索順位も下がってしまうため、少なくとも1ヶ月に1回は更新するのがおすすめです。
自社で更新作業をしない・できない場合は、制作を依頼したホームページ制作会社に運営管理を依頼しましょう。
セキュリティ対策を怠る
セキュリティ対策も、ホームページの運営において重要なポイントです。
サーバーのパスワードの適切な内容と適度な更新
サーバーのパスワードの更新はセキュリティ対策の基本です。他者が推測しやすいパスワードを使ったり、ずっと同じパスワードを使っていると、外部からハッキングされて内容を改ざんされたり削除されてしまう恐れがあります。
サーバーのパスワードはある程度複雑にして適切に管理し、一定期間ごとに変更するようにしましょう。
情報やアクセス権限の管理
ホームページの運営を行う上で、ユーザーの個人情報など、外部に流出させられない機密情報を扱う機会もあります。
重要な情報ほどアクセス権限に気をつけ、誰が閲覧・編集・コピー・持ち出しなどをできるように設定するかはっきりさせておきましょう。
8.まとめ
今回はホームページ制作でやってはいけないことをご紹介しました。
上記で紹介したNGリストに当てはまるからといって、必ずしも成果が出ないサイトというわけではありませんが、できるだけ正しい方法で制作できるのが理想です。
また著作権や薬機法など法律に関わる箇所に関しては、必ずルールを守って制作する必要がありますので、注意してください。
今回ご紹介した知識を、制作会社選びやホームページの制作に役立ててみてください。
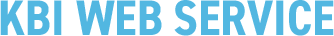


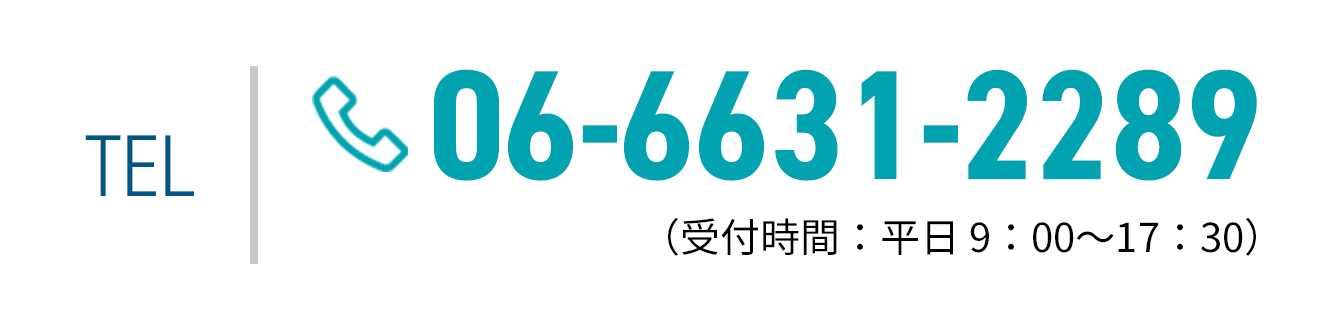

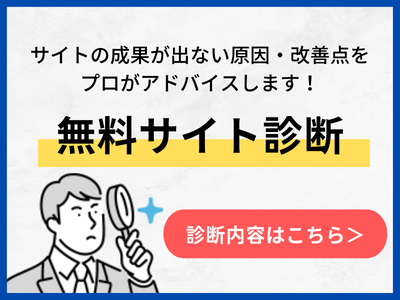
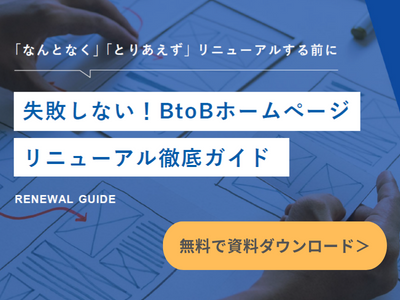
.png)
.png)