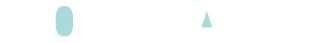コラム
ホームページ制作の料金相場は?制作会社を選ぶ注意点、自作ソフトも紹介
ホームページ制作は、事業運営の第一歩と言える重要なステップです。プロの制作会社に委託して作ってもらうこともできますし、近年は自分でホームページ制作ができるツールも増えています。
今回は、ホームページ制作を依頼する場合の費用相場や、制作会社選びのポイントについて解説!
おすすめのホームページ制作ツール7選もご紹介します。
CONTENTS
1.ホームページ制作費用の相場
まずは、ホームページを制作会社に依頼して作る場合の費用相場についてお伝えします。
相場は40万円前後から
ホームページを外部委託して作る場合の費用は、40万円〜くらいが相場です。
料金は基本的に作業工程の多さと比例します。ページ数やデザイン次第では100万円以上かかるケースも。
また、当然ですが制作会社によっても料金設定は異なりますので、注意が必要です。
安いホームページ制作会社は大丈夫?
ホームページ制作会社の中には、相場より安い料金で請け負っている会社もあります。
料金が安い理由は、「料金を下げてでも仕事を獲得したいから」もしくは「料金を安くできる仕組みやノウハウがあるから」と言えるでしょう。
前者の場合、例えば立ち上げて間もない会社など、利益度外視でも実績を作りたい、新規顧客を獲得したいという理由が考えられます。
また、制作はできても集客効果が高くないなど、成果物のクオリティがいまいちで、その値段でないと顧客がつかないというケースも。後者の場合は、制作費用を安くして、その後の保守・運営料金で利益を得ているケースなどが考えられます。
ホームページ制作会社を選ぶ際、安さだけではなく様々な角度から検討した方がよいでしょう。
2.ホームページ制作の目安の料金表

一般的なホームページ制作費用の目安は、以下の表のようになります。
| ホームページの種類 | 料金 | 主な内容・機能 |
| ・小規模コーポレートサイト ・オウンドメディア |
40万円〜 | ・ページ数10ページ以内 ・テンプレートやCMSを使用したデザイン ・画像やテキストは依頼者側で用意 |
| ・中規模コーポレートサイト
・ECサイト ・リクルートサイト |
100万円〜 | ・ページ数20ページ前後
・オリジナルデザイン ・独自コンテンツ ・決済機能 ・ショッピングカート機能 |
| ・大規模コーポレートサイト
・ポータルサイト |
150万円〜 | ・ページ数30ページ前後
・プロによるコンサルティング ・集客力の高いオリジナルデザイン ・トレンドのコンテンツ |
| ・より大規模なコーポレートサイト/ポータルサイト | 200万円〜 | ・複数ジャンル/ブランドにまたがるポータルサイト
・SNSとの連動 ・クオリティの高い動画・コンテンツ |
※CMSとは「Contents Management System:コンテンツ・マネジメント・システム」の略。Webサイトのコンテンツを構成するテキストをはじめ画像、デザインやレイアウト情報等を一元化して保存と管理を行うシステム。
3.ホームページ制作費用に差が出るポイント

ここでは、ホームページ制作において、費用に差が出るポイントを4つご紹介します。
ページ数
ホームページの制作費用は、まずページ数に比例します。
ページ数とは、そのホームページがいくつの「画面」で構成されているかで数えます。
例えば採用サイトで「トップページ」「会社概要」「事業内容」「応募要項」「問合せフォーム」のそれぞれのページを作った場合、このホームページは5ページで構成されているということです。
コンテンツやメニュー数が多いほど、ページ数が多くなり制作費用も追加されます。
【1ページあたりの制作費用の目安】
トップページ:7〜20万円
下層ページ:2〜8万円/1ページ
デザイン
デザインは、凝れば凝るほど費用がかかってくる部分です。センスの良い人気デザイナーに依頼したり、アニメーションをつけるなどをすると費用がかさみます。
また、トレンドのデザインを掴むためにコンサルを受けると、別途でコンサル料がかかる制作会社もあります。
ホームページの機能自体を左右するわけではありませんが、サイトの見た目やクオリティは企業のイメージや集客力に大きく関わるため、重要な部分です。
機能
ホームページに特別な機能をつける場合、そのぶん費用がかかります。
例えば、「ショッピングカート」「問合せフォーム」「決済機能」「会員登録機能」「SNSとの連動」のような機能です。これらの機能をつけるにはシステムの構築やコーディングが必要で、独自性・複雑性の高い機能になるほど料金が上がります。
逆に特別な機能が必要ない、テキストページなどは制作費用が安いです。
SEO対策
SEO対策とは、「検索エンジン最適化」のことで、ホームページの内容をGoogleなどの検索エンジンが理解しやすいように工夫することを言います。
SEO対策をすると、検索結果の上位に表示されるようになり、アクセス数の向上が期待できます。SEO対策を標準仕様にしている制作会社と、追加費用がかかる制作会社があり、別途の場合は5万円〜くらいが相場です。
SEO対策の方法やクオリティは会社によってまちまちなので、その会社の実績を調べておきましょう。
4.ホームページ制作会社選びに失敗しないポイント

ここでは、ホームページの制作会社依頼に失敗しないために、知っておきたい3つのポイントをお伝えします。
制作する目的と制作会社の強みが合致しているか
ホームページの制作会社によって、強みはさまざまです。その会社のコンセプトや設立経緯、実績などによって、得意とするホームページのジャンルや業界、ターゲットなどが異なります。
例えば、デザインやブランディングを軸とした会社に、集客やマーケティング重視のホームページを依頼してもあまり成果は出ないでしょう。
ホームページ制作会社を選ぶときには、その会社の実績や強みが自分のニーズに合っているかどうかをまずチェックするのがおすすめです。
相見積もりを取り妥当な価格を判断する
ホームページの制作を依頼するのが初めての場合、1社の見積もりだけでは正確な相場を判断するのが難しいです。
見積もりは何社とっても問題ないので、目星をつけたいくつかの制作会社に見積もりを依頼し、価格や内容を比較しましょう。
ただし、単純に価格を比べるだけではなく、提案内容も重要です。自分のニーズをうまく汲み取り、そこにどのような解決策を提示してくれるのか、その上で料金が妥当かどうかを判断しましょう。
制作後の対応も確認
ホームページは、単に制作するだけではなく、その後の保守・運営も重要です。
不具合の修正やメンテナンスなど最低限の運用だけではなく、アクセス解析やSNSの運用代行などを行ってくれる会社もあります。
制作後にどのような対応やサポートが受けられるのか、またホームページの維持にかかる費用についても確認しておきましょう。
制作費用自体は安い分、この保守・運営費用を高めに設定している会社もあるため注意が必要です。
5.自分でホームページを制作するツール7選
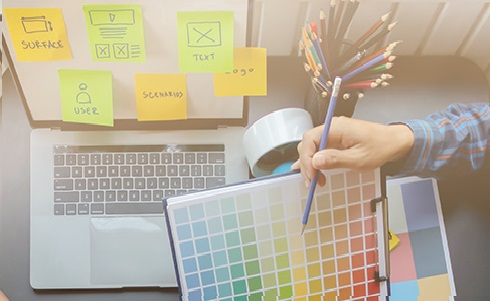
ホームページ制作は外部委託するだけではなく、自分で行うこともできます。
知識がない人でもホームページを制作しやすい、おすすめのツールやプラットフォームを7選ご紹介します。
Wix
Wixは、イスラエルに本社を置くクラウドタイプのCMSです。
基本プランは無料で利用でき、特別な知識がなくてもドラッグ&ドロップでホームページが作れるのが特徴となっています。
Wixのメリット
Wixのメリットは、とにかく直感的に操作ができること。
HTMLやCSSのWEB知識がなくても、あらかじめ用意されているコンテンツをクリックするだけでページが作成できます。
マウス操作で追加した要素を自由に動かすことができるので、自由なレイアウトができるのも特徴的です。
追加できる要素にはアニメーションも含まれるので、動きのあるホームページも簡単に制作できます。
また、基本プランは無料なので、メールアドレスだけ用意すれば誰でも気軽にホームページ制作ができるのもWixの魅力です。
Wixのデメリット
Wixのデメリットは、レイアウトの自由度が高いぶんデザインセンスが問われること。
また、一度選択したテンプレートは途中で変更できないため、事前にしっかりとイメージを持って作り始める必要があります。
さらに、無料版だと「独自ドメインが使えない」「Wixの広告が埋め込まれている」といった制限があるため、事業用ホームページの場合は有料プランにアップデートする必要があるでしょう。Wixの有料プランは、月額500円から2,500円までの4プランがあります。
Jimdo
Jimdoは、ドイツのJimdo GmbH社が提供しているクラウドタイプCMS。
Wixと同様、プログラミングなどの知識がなくても簡単にホームページ制作ができます。
最大の特徴は、質問に答えていくことで半自動的にホームページが出来上がる「ジンドゥーAIビルダー」です。
Jimdoのメリット
Jimdoを利用するメリットは、「ジンドゥーAIビルダー」の機能によって、自分ではほぼ何も作業しなくてもある程度のクオリティのホームページが作れること。
また、iOS用とAndroid用のアプリがあるため、スマホから更新や編集作業ができることも特徴です。
Jimdoで制作したホームページは「レスポンシブレイアウト」で表示されるため、スマホやタブレットで最適な表示ができることもメリットと言えるでしょう。
18種類のSNSとの連動も可能なため、ユーザーにシェア機能を利用してもらいたい場合にもおすすめです。
Jimdoのデメリット
Jimdoのデメリットは、無料版だと制限が多いこと。
「独自ドメインが使えない」「広告が埋め込まれている」「SEOの細かい設定ができない」といった制限のほか、ECサイトの場合は無料版だと5つまでしか商品を登録できません。
事業用に使用するためには、有料プランへのアップデートが必要になるでしょう。
Jimdoの有料プランは、月額965円から5,190円までの4プランがあります。また、最大の特徴であるジンドゥーAIビルダーの利用にも追加料金が必要です。
WordPress
WordPressは、世界で最もシェア率の高いCMS。
有料プランがなく、完全無料で利用できるので、個人から法人まで幅広く利用されています。
オープンソース型として誰でもアクセスできるように公開されているため、有志のエンジニアによって常にバージョンアップされていることも特徴です。
WordPressのメリット
WordPressは、無料でページ数の制限がないホームページが制作できるのがメリットです。
また、「テーマ(テンプレート)」や「プラグイン(拡張機能)」が豊富で、これらを組み合わせることで、知識のない人でも独自性の高いホームページを作ることができます。
元々ブログ用のCMSとして広まったため、ブログやアフィリエイトサイトの制作・運営に適しているのも大きな特徴です。
WordPressのデメリット
WordPressのデメリットは、サーバーやドメインを自分で用意する必要があること。
無料ブログのレンタルドメインや、WordPressの初期ドメインもありますが、事業用にGoogleアドセンスなどを使用したい場合は独自ドメインが必要です。
また、無料で利用できるサービスなのでサポートはなく、何か問題が発生した場合は自分で対処する必要があります。
しかし、シェア率が高いサービスということもあり、ネット上に情報が豊富なので、解決策は比較的見つけやすいでしょう。
STUDIO
STUDIOは、コーディングなしで簡単にホームページが作れるツール。
ゼロからデザインしていく方法と、テンプレートから作る方法を選べるのが特徴です。
無料で使えてサーバー設定も必要ないため、とにかく手軽にホームページ制作をしたい人におすすめです。
STUDIOのメリット
STUDIOのメリットは、複雑な作業が不要でドラッグ&ドロップのみでホームページを作れること。
また、制作したデザインは1クリックでWebサイトとして公開できるため、とても作業が簡単です。
単純なデザインだけではなく、アニメーションをつけることもできます。
また、日本のSTUDIO株式会社が運営しているので、日本語で説明やサポートが受けられるのも魅力です。
STUDIOのデメリット
STUDIOのデメリットは、コードを触って微細な調整や編集ができないこと。
ノーコードツールなので、ドラッグ&ドロップでできる範囲でしか設定ができません。
デザインに強いこだわりがある人には不向きなツールと言えるでしょう。
無料プランには「STUDIOのロゴが入る」「公開できる記事が5つまで」などの制限があり、事業用に使用するには月額980円または2,480円の有料プランにアップデートする必要があります。
STORES
STORESは、日本のヘイ株式会社が提供しているサービスです。
STORESという名称の通りネットショップの制作に特化していて、ホームページ制作以外にショップのさまざまな業務をデジタル化できます。
STORESのメリット
STORESは、初期費用0円で気軽にネットショップを制作できるのがメリットです。
決済手数料はかかりますが、無料プランなら5%と良心的で、月額2,178円の有料プランでは3.6%と業界最低水準となっています。
また、Instagramとの連携が簡単で、Instagramでの集客に力を入れたい人におすすめ。
商品の販売だけではなく、ニュース配信、再入荷通知、FAQ作成、ギフト設定などの便利な機能が使えるのもポイントです。
STORESのデメリット
STORESのデメリットは、コード編集ができず、デザインの微細な調整に対応していないこと。
また、無料プランでは独自ドメインやアクセス解析、STORESロゴの非表示など一部の機能を使うことができません。
STORES自体が集客するような機能もないため、集客やマーケティングに関しては自分で考えて工夫する必要があります。
BASE
BASEは、日本国内で最もシェア率の高いネットショップ制作サービス。
無料で簡単にネットショップの立ち上げを行うことができ、CMなども流れていて知名度が高いです。
BASEのメリット
BASEのメリットは、国内での知名度が高く、ショッピングアプリもあるため集客効果が期待できること。
楽天などのモール型ネットショップほどではありませんが、他のネットショップ制作サービスに比べると顧客の目に留まりやすいです。
また、「BASE かんたん決済」という機能により、通常は審査に時間がかかることが多いクレジットカード決済も、ショップ立ち上げ間もない時期から利用できます。
BASEのデメリット
BASEのデメリットは、決済手数料がやや高めなこと。
ネットショップ制作や運営費用は無料ですが、「BASEかんたん決済手数料」として3.6%+40円、「サービス利用料」として3%がかかります。
利用者が「BASEかんたん決済」で決済した場合、6.6%+40円の手数料がかかるということです。
また、ホームページ制作に関しては簡単さを優先しているため、機能やテンプレートのバリエーションは他のCMS等に比べると少なめになっています。
カラーミーショップ
カラーミーショップは、GMOペパボ株式会社が運営しているネットショップ制作サービスです。
2005年にスタートした息の長いサービスで、個人・法人を含めて4万店舗以上の導入実績があります。
カラーミーショップのメリット
カラーミーショップは、東証一部上場企業が運営するサービスです。
また、4万店舗以上が導入していて、その6割以上は3年以上カラーミーショップの利用を継続しているなど、信頼感があるのがメリット。
また、クレジットカード払いだけではなく、後払い、コンビニ払い、代引き、Amazon Pay、楽天ペイなど、決済方法が豊富なのもポイントです。
月額の有料プランは決済手数料が0円なので、初期費用より運営費用を節約したい人におすすめです。
カラーミーショップのデメリット
カラーミーショップのデメリットは、無料プランの決済手数料が高めなこと。
フリープランは決済ごとに6.6% + 30円の決済手数料がかかります。
有料プランは月額4,950円と9,595円のコースがあり、これらのプランだと決済手数料は売り上げ金額に関わらず0円です。
また、無料テンプレートの種類があまり多くないため、ショップデザインにこだわりにくいこともデメリットと言えるでしょう。
6.まとめ
ホームページ制作を外部委託するための費用は、小規模や簡易なデザインであれば40万円〜くらいが相場です。
相場より安い制作会社もありますが、それなりの理由があったり、初期費用は安くても保守・運用に費用がかかることもあります。
自分でホームページ制作ができるツールも増えていますが、制作後に本当に効果が出るホームページを作ろうと思えば、やはりプロである制作会社に一度相談するのがおすすめでしょう。
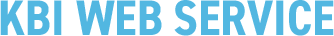


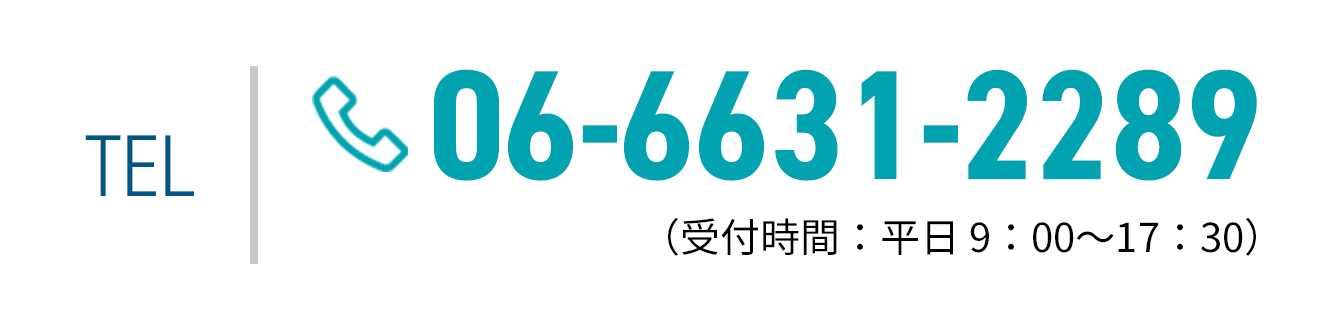

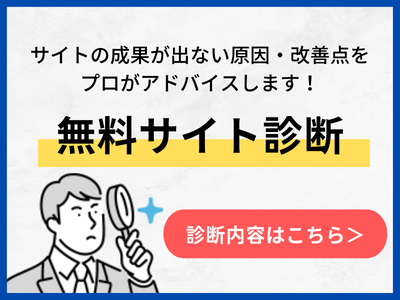
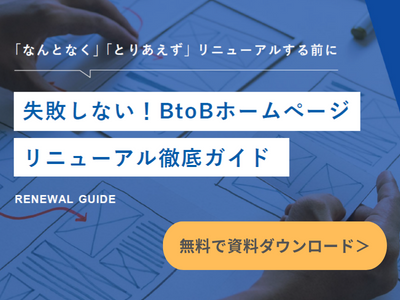
.png)
.png)